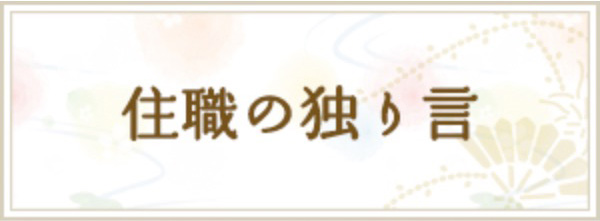天真寺通信
盆踊りの由来

こちらは、築地本願寺盆踊りの写真です。
本日、築地本願寺の朝のお参りにて、先生が、盆踊りの起源の諸説のある中、一遍上人の念仏踊りについてお話し下さいました。
盆踊りの起源
一遍聖人が、念仏をひろめるために念仏を称え、踊り念仏に発展していった。文字の読めない方がたくさんいらっしゃる時代、身振り手振りで身体で記憶し、今日まで弘まっていったというお話でありました。
CHATGPT先生にも尋ねてみました!!!
盆踊りの起源 CHATG先生
盆踊り(ぼんおどり)の起源は、日本の仏教行事「盂蘭盆会(うらぼんえ)」にさかのぼります。これは祖先や亡くなった人々の霊を慰めるための行事で、平安時代ごろから広まりました。以下に詳しく説明します。
1. 盂蘭盆会と目連尊者の物語
- 盆踊りの元になった「盂蘭盆会」は、仏教の経典『盂蘭盆経(うらぼんきょう)』に基づきます。
- 釈迦の弟子である**目連尊者(もくれんそんじゃ)**が餓鬼道に堕ちた母を救うため、釈迦の教えに従って多くの僧に施しをしたところ、母が救われました。
- 母が救われた喜びのあまり、目連尊者が踊ったとされるのが「踊り」の由来のひとつです。
2. 日本への伝来と変化
- 仏教が日本に伝わった奈良・平安時代には、盂蘭盆会が貴族・寺院中心の行事として行われていました。
- 鎌倉時代〜室町時代にかけて、民衆の間にも広がり、精霊を迎えて供養する行事として定着します。
- この頃、念仏を唱えながら踊る念仏踊りや、神楽・風流踊りなどの民俗芸能と融合し、現在の盆踊りの形に近づきました。
3. 民衆の娯楽としての発展
- 江戸時代になると、盆踊りは供養の意味だけでなく、村人同士の交流・娯楽としても盛んに行われるようになりました。
- 夜通し踊る中で、若者たちの出会いの場にもなり、地域ごとに独自の歌や踊りが生まれます。
4. 現在の盆踊り
- 祖霊供養の意味を持ちながらも、地域の伝統文化・お祭りとして発展。
- 地方によって踊りや音楽が大きく異なり、例えば**郡上踊り(岐阜)や阿波踊り(徳島)**などは全国的に有名です。
まとめ
- 起源:仏教の盂蘭盆会(目連尊者の母親救済の物語)
- 発展:念仏踊りや民俗芸能と融合して日本各地に広がる
- 意味:祖先供養+地域の交流・娯楽
💡 実は、盆踊りの「踊り」部分には霊を迎え、また送り出す動作の意味もあるとされます。宗教的な儀礼と、村の社交・祭りが合わさった独特の文化なんですね。
さまざまな歴史を通して、盆踊りが伝わってきているのですね。
改めて、先人達のことを思いながら、盆踊りに参加してみたいと思った、今日この頃です。
ちなみに、昨日から築地本願寺にて盆踊りが開催中です。
2025年築地本願寺盆踊りby築地本願寺HP
https://tsukijihongwanji.jp/news/10279
カテゴリ
- 住職の独り言 (5)
- お寺の活動 (443)
- みんなの日曜礼拝 (337)
- 仏教壮年会 (36)
- 仏教婦人会(れんげ会) (12)
- 天真寺ふれあい農園 (13)
- 天真寺キッズクラブ (26)
- お寺の行事 (71)
- イベント (61)
- グループ (9)
- ボラン寺(お寺でボランティア) (36)
- 天ちゃん募金 (2)
- お寺の国際協力 (5)
- がんばっぺ福島 (11)
- チャリティー雅楽演奏会 (3)
- ペットボトルキャップ回収 (8)
- メディア情報 (36)
- 五大法要 (130)
- 京都 (68)
- 京都たより (4)
- 仏教Q&A (5)
- 墓地 (174)
- 大町やすらぎパーク (4)
- 永代合葬墓あんのん堂 (147)
- 永代合葬墓やすらぎ堂 (26)
- 天真寺 (531)
- 勤式 (1)
- 寺報「月刊てんしん」 (68)
- 島根浄圓寺 (13)
- 法話 (16)
- 蓮(ハス) (91)
- オンライン配信 (142)
- 天ちゃん (14)
- 天ちゃんねる(天真寺WEB) (37)
- 寺子屋 (69)
- クリスタルボウルヨガ (13)
- グランドゴルフ (13)
- ヨーガ教室 (2)
- 天真寺雅楽教室 (37)
- 掲示板 (4)
- 未分類 (800)
- 本願寺 (171)
- 築地本願寺 (132)
- 法話 (64)
- 落語 (1)
- 講演関係 (49)
- 関係団体 (28)
- 未分類 (227)