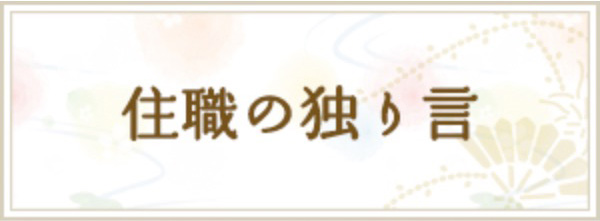天真寺通信
孟蘭盆会の語源

明日から8月14日15日二日間にわたり午前から新盆法要、午後から孟蘭盆会法要が勤まります。講師は、鎌田宗雲師であります。今日は、御門徒の皆様によって、本堂椅子の増設などをしてくださり、明日の法要に供えます。いつもお手伝い有り難うございます。
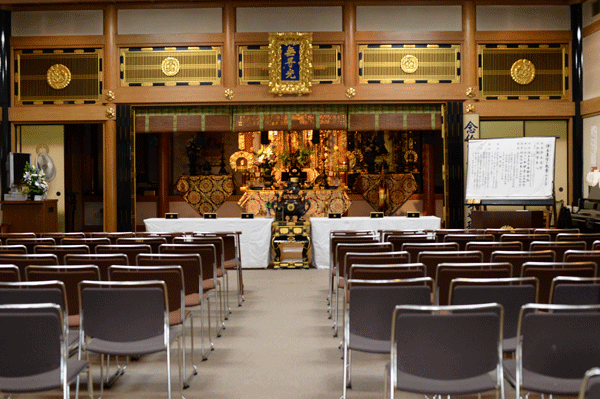
仏様目線からみた本堂

インターネットを検索している、4年前にに話題になった「孟蘭盆」の本当の語源について中外日報さんの記事がアップされていた。
[中外日報 「盂蘭盆」の本当の意味 ―「ご飯をのせた盆」と推定]
http://www.chugainippoh.co.jp/ronbun/2013/0725rondan.html
これまでは「盂蘭盆」とは「倒懸・逆さづりの苦しみ」の意味とされてきたが、中外日報さんによると「お盆」という意味のようです。
以下、中外日報さんより掲載。
『盂蘭盆経』(本来は『盂蘭経』であり、7世紀から『盂蘭盆経』と呼ばれ始めた)に、「盂蘭盆」という語は三度出る。
①(僧侶たちに)盂蘭盆を捧げなさい(応奉盂蘭盆)
②(自恣の日に)百味の飲食物を盂蘭盆の中にいれて(僧侶たちに施しなさい)(以百味飲食安盂蘭盆中)
③(毎年7月15日に)父母のために盂蘭盆を作って、仏と僧侶たちに施しなさい(作盂蘭盆施仏及僧)
この三つの語句から、自恣の日に僧侶たちに施す、食べ物を盛る容器、またその食べ物自体を「盂蘭盆」といっていることは明らかである。従って「盆」は容器としてのお盆という通常の意味に他ならない。「盂蘭」は原語の音を転写した音写語で間違いなかろう。
とあります。
ですが、この記事は4年前に紹介されましたが、なかなか一般化されていません。やはり、「孟蘭盆会⇒目連尊者⇒目連尊者の母⇒ウランバナー(逆さづりの苦しみ)⇒救われる」という何十年と蓄積されたイメージは崩れないのだろう。最後に、盂蘭盆経は中国でつくられた偽経といわれてきたが、そうではないようであります(^_^)
記事によると、
この経典に見える漢語語彙は、鳩摩羅什の訳した経典(401~413年に訳出)に見えるものよりも古風で、竺法護の用法に似ている。この経は偽経ではなく、3、4世紀に竺法護か誰かによって、インドの原典から訳された経典である。
とのことであります。
なによりも、明日天真寺本堂にて、新盆法要、孟蘭盆会法要が厳修されますので、ぜひご参拝くださいませ。
カテゴリ
- 住職の独り言 (5)
- お寺の活動 (436)
- みんなの日曜礼拝 (330)
- 仏教壮年会 (36)
- 仏教婦人会(れんげ会) (12)
- 天真寺ふれあい農園 (13)
- 天真寺キッズクラブ (26)
- お寺の行事 (70)
- イベント (61)
- グループ (9)
- ボラン寺(お寺でボランティア) (36)
- 天ちゃん募金 (2)
- お寺の国際協力 (5)
- がんばっぺ福島 (11)
- チャリティー雅楽演奏会 (3)
- ペットボトルキャップ回収 (8)
- メディア情報 (36)
- 五大法要 (130)
- 京都 (67)
- 京都たより (4)
- 仏教Q&A (5)
- 墓地 (171)
- 大町やすらぎパーク (4)
- 永代合葬墓あんのん堂 (144)
- 永代合葬墓やすらぎ堂 (26)
- 天真寺 (527)
- 勤式 (1)
- 寺報「月刊てんしん」 (67)
- 島根浄圓寺 (13)
- 法話 (16)
- 蓮(ハス) (91)
- オンライン配信 (141)
- 天ちゃん (14)
- 天ちゃんねる(天真寺WEB) (37)
- 寺子屋 (69)
- クリスタルボウルヨガ (13)
- グランドゴルフ (13)
- ヨーガ教室 (2)
- 天真寺雅楽教室 (37)
- 掲示板 (4)
- 未分類 (800)
- 本願寺 (166)
- 築地本願寺 (132)
- 法話 (63)
- 落語 (1)
- 講演関係 (49)
- 関係団体 (28)
- 未分類 (220)